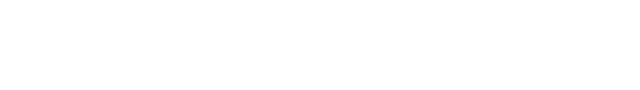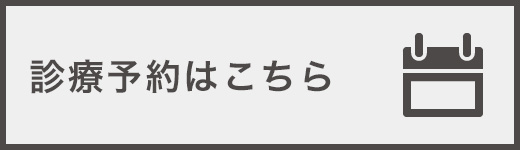妊婦健診
妊娠された方へ
妊娠初診
生理予定日を過ぎても生理がこない場合には、ぜひ市販の妊娠反応検査薬を使用して妊娠のチェックをしてみましょう。もちろん当院でこのチェックをすることもできます。陽性反応が出た場合にはぜひ受診してみてください。受診する時期は生理予定日から1-2週間経過したあたりをおすすめいたします。この時期になると子宮の中に胎のう(赤ちゃんが入っている袋)が見えてきますので、それを超音波で確認します。
※妊娠の診療は自費になります。初診では、およそ6,000円ほどかかります。
妊娠初期(妊娠2-3カ月あたり)
胎のう確認後は2週間ほどで赤ちゃんの心拍(心臓の動き)が確認できるようになります。この心臓の動きは超音波でみてわかるもので、実際に音としてきこえるようになるのは妊娠12週以降です。心拍が確認された時点で分娩をする病院の検討を始めることをおすすめします。
心拍確認からさらに2週間ほどすると赤ちゃんの頭や体がわかるようになってきます。この頃には最終月経開始日や超音波の画像所見から出産予定日の決定をおこないます。予定日が決定するとお住まいの自治体で母子手帳の交付を受けることができます。予定日が決まったら、そろそろ分娩先を探し始めましょう。12週頃までには決めておくことが望ましいです。
分娩先受診の際に紹介状が必要となる場合には、こちらで用意いたします。その場ですぐ発行はできませんので、前日までに必要な旨をお申し出ください。
当院ではセミオープンシステムによる妊婦健診をおすすめしています。現在聖路加国際病院や、昭和大学江東豊洲病院、愛育病院、東大付属病院等でのセミオープンシステム利用が可能となっております。都外で里帰り出産する方も、セミオープンシステム(里帰り)を登録のうえで当院での妊婦健診が可能ですので、ぜひご利用ください。34週頃までは、当院での健診を続けることができます。セミオープンシステム対応病院以外の出産でも当院にて妊婦健診対応ができることも多いので、ますは受診時にご相談ください。
妊婦健診とは
母子手帳取得後は妊婦健診をしていくことになります。
妊婦健診は、お母さんとおなかの赤ちゃんの健康を守り、妊娠が順調かどうかをチェックするための健診です。
妊婦健診で行う検査には多くのものがありますが、どれも母体と赤ちゃんの健康を確かめるための、大事なものばかりです。
具体的な妊婦健診項目
(1)妊娠初期に行う検査(妊娠8週から10週の頃におこないます)
- 血液検査
(血液型;ABO式、Rh式/不規則抗体検査/貧血の有無/梅毒血清反応/B型肝炎ウイルス抗原検査/C型肝炎ウイルス抗体検査/風疹ウイルス抗体検査/HIV抗体検査/血糖値検査)
*風疹ウイルス抗体価が高い場合には追加検査(風疹IgM抗体価検査)を行います。
*血糖値が高い場合は追加検査(糖負荷テスト)を行います。
(2)定期妊婦健診で毎回行う検査
- 超音波検査にて胎児の大きさ、位置、胎児心拍の確認
- 体重測定
- 血圧測定
- 尿検査(たんぱく、糖)
- むくみの有無 など
(3)妊娠中期に行う検査
- 胎児スクリーニングエコー(胎児の心臓や頭部、内臓などを詳しく検査します)
セミオープンの方はセミオープン先にて受けていただくこともできます。また希望の方は胎児スクリーニングエコーだけを他院で受診するといったこともできます。 - 妊娠糖尿病スクリーニング検査(50g糖負荷テスト)
- 貧血検査
- クラミジア抗原、腟分泌物培養検査
- HTLV-1抗体検査
(4)その他希望に応じて行う検査
希望により以下の検査を追加することもできます。
- トキソプラズマ抗体検査
- サイトメガロウイルス抗体検査 など
*以上のほかの検査も、必要な場合には随時実施いたします。
34週頃以降は、分娩先の病院で健診を受けていただきます。当院での最後の受診時に紹介状をお渡しいたしますので、事前にお申し出ください。当日に紹介状希望の申し出があった場合は、後日のお渡しとなります。